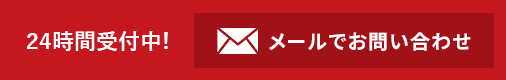雨樋修理・交換の際に足場の必要性や費用はいくらかかるの?
あまどい屋 日本住宅診断株式会社 TOP > 雨樋修理・交換の際に足場の必要性や費用はいくらかかるの?
雨樋修理・交換の際に足場の必要性や費用はいくらかかるの?をお伝えします。
雨樋修理・雨樋交換のあまどい屋です。
「雨どい修理・交換の際に足場の必要性や費用はいくらかかるの?」
と質問をもらいました。
お客様の中には、
料金を下げるために足場なしで
お願いと言ってくる方もいます。
業者からすると無理だろと思うケースもございます。
その時は、お断りをさせてもらっています。
以前、知恵袋を見たときに
ビケ足場から単管足場に変えたらどのくらい安くなりますか?
という記事を見て
怖い人が世の中にいるもんだなと感じたことを思い出しました。
単管だと塗装とかならまだしも、雨どいはできないです。
そういうお客様とは取引したくないものですね。
さて本題に移ります。
雨樋の修理を考えはじめた時、足場を組んでもらう必要があるのか、
どのくらい費用がかかるのか気になりますよね。
雨樋修理する際足場を設置する必要があるのかというところから話していきます。
雨樋の修理に、「足場を組まなければいけないのか」と疑問に思う方は多いと思います。
「ハシゴに上って修理することはできないの?」と思う方もいるのではないでしょうか。
足場の設置は有料の為、できることなら削減したいですよね。
気持ちはわかります。
しかし、原則 2階部分は必要になります。
雨樋を修理する箇所にもよりますが、2階部分の修理の場合は、どうしても足場が必要になります。
ただ、一部分の金具が外れていたり、小規模の場合はハシゴを使って修理するケースもあります。
ですが、雨樋全体の交換や、大規模の修理になると足場が必要になります。
足場代を押さえたい気持ちもありますが、安全性を考えると足場は設置しなければならないのです。
一方1階部分は不要
1階部分の雨樋修理の場合、足場は不要です。また、平屋住宅の場合、足場を設置せずそのまま修理が行えます。
なぜなら、脚立に道板(みちいた)と呼ばれる板をかける事によって、簡易的な足場が出来るからです。
ただし、1階部分であっても高台であったり、崖に面していたりする場合はこの方法で修理が行えません。
では2階部分で足場費用は一体いくらかかるのか?です
雨樋がある部分に必要な所に組む為、10~25万円程度の費用になります。
ただし、首都圏などの都市部になると費用は高くなるため、あくまでも目安にしていただきたいです。
修理には火災保険も利用できるので、一度専門業者の無料診断をしてもらいましょう。
「雨どい修理・交換の際に足場の必要性や費用はいくらかかるの?」
と質問をもらいました。
お客様の中には、
料金を下げるために足場なしで
お願いと言ってくる方もいます。
業者からすると無理だろと思うケースもございます。
その時は、お断りをさせてもらっています。
以前、知恵袋を見たときに
ビケ足場から単管足場に変えたらどのくらい安くなりますか?
という記事を見て
怖い人が世の中にいるもんだなと感じたことを思い出しました。
単管だと塗装とかならまだしも、雨どいはできないです。
そういうお客様とは取引したくないものですね。
さて本題に移ります。
雨樋の修理を考えはじめた時、足場を組んでもらう必要があるのか、
どのくらい費用がかかるのか気になりますよね。
雨樋修理する際足場を設置する必要があるのかというところから話していきます。
雨樋の修理に、「足場を組まなければいけないのか」と疑問に思う方は多いと思います。
「ハシゴに上って修理することはできないの?」と思う方もいるのではないでしょうか。
足場の設置は有料の為、できることなら削減したいですよね。
気持ちはわかります。
しかし、原則 2階部分は必要になります。
雨樋を修理する箇所にもよりますが、2階部分の修理の場合は、どうしても足場が必要になります。
ただ、一部分の金具が外れていたり、小規模の場合はハシゴを使って修理するケースもあります。
ですが、雨樋全体の交換や、大規模の修理になると足場が必要になります。
足場代を押さえたい気持ちもありますが、安全性を考えると足場は設置しなければならないのです。
一方1階部分は不要
1階部分の雨樋修理の場合、足場は不要です。また、平屋住宅の場合、足場を設置せずそのまま修理が行えます。
なぜなら、脚立に道板(みちいた)と呼ばれる板をかける事によって、簡易的な足場が出来るからです。
ただし、1階部分であっても高台であったり、崖に面していたりする場合はこの方法で修理が行えません。
では2階部分で足場費用は一体いくらかかるのか?です
雨樋がある部分に必要な所に組む為、10~25万円程度の費用になります。
ただし、首都圏などの都市部になると費用は高くなるため、あくまでも目安にしていただきたいです。
修理には火災保険も利用できるので、一度専門業者の無料診断をしてもらいましょう。